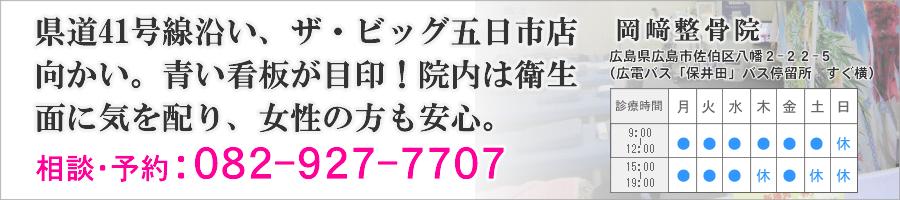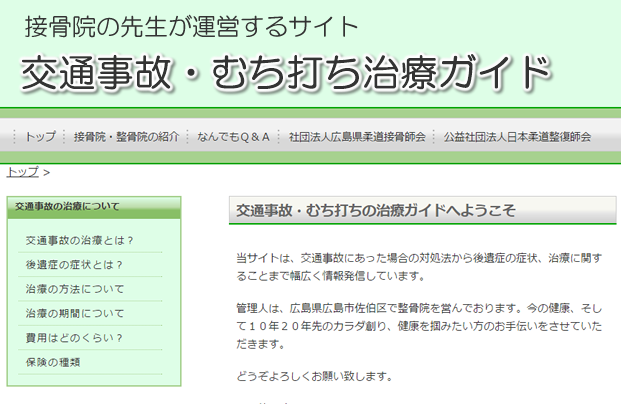・アスタキサンチン
緑黄色野菜に含まれるカロテノイドと呼ばれる色素の一種で、サケやエビ、カニなどの赤い色をした魚介類に含まれます。
アスタキサンチンの抗酸化力は非常に高く、抗酸化力のあるビタミンEよりも高いと言われています。体の酸化を抑えることで、体の老化や血液中のLDLコレステロールの酸化も防ぎ、動脈硬化を予防するとも言われています。紫外線があたることにより発生する活性酸素を取り除く働きもあり、シミやシワなどの予防にもなります。
その他、免疫力を正常化させたり、脳細胞を活性酸素から守るため、認知症の予防効果もあるといわれています。
(さらに…)
何の前触れもなく足がつってしまう・・・足がつる原因はさまざまですが、食事で予防することも出来ます。
こむら返りや足がつるとは?
『足がつる』とは、足の筋肉が突然強い痙攣を起こす状態のことをいいます。
特にふくらはぎ(こむら)に起こることが多く、それを『こむら返り』といいます。
原因はさまざまです。
こむら返りの原因
◆栄養不足
カルシウムやマグネシウム、ナトリウム、カリウムといったミネラルや、ビタミンB1やタウリンといった栄養素が不足していると、筋肉や神経が興奮しやすくなったり、疲労しやすくなったりする為に起こることがあります。
◆水分不足、汗をたくさんかく
水分が不足すると血行が悪くなり、その影響で筋肉が収縮して起こることがあります。また、汗をたくさんかくと筋肉や神経に必要なビタミンやミネラルが不足して起こることがあります。
(さらに…)
膝の仕組みと痛み
膝は「おさら」と呼ばれる膝蓋骨と、大腿骨と、脛骨という3つの骨から成り立っています。これらの骨は関節軟骨に覆われています。
関節軟骨と半月板は、骨と骨のつなぎ目を保護し、摩擦を最小限にすることによって、膝にかかる衝撃を吸収する働きをしています。
○関節軟骨・半月板…クッションの役目をしています。
○関節液…潤滑油として、関節がなめらかに動くように助けています。
なぜ膝に痛みが起こるのでしょう?
膝の痛みに悩む患者さんは中高年層が覆いといえます。年を重ねるとともに、クッションの役目をする軟骨が弱くなり、その負担に耐えられなくなるためです。
膝の痛みで最も多いのが、変形性膝関節症です。男性よりも女性の患者さんが多いといえます。 (さらに…)
五十肩って何?
五十肩とは”五十歳頃、肩を中心に痛みが生じ、時に腕まで広がり、やがて自然に治っていく状態”に対して、古くから使われてきた言葉です。
現在では、一般的に”肩関節周囲炎”と呼ばれる状態を五十肩といいます。
五十肩の3つの病期
痛みの程度や性質によって治療が違います。自己判断はダメ。専門家の指示による正しい治療を受けましょう。
フリージング期…五十肩の初期(筋痙縮期)
●炎症が、するどい痛みを引き起こします。
●さらに、この痛みが筋肉のけいれんを引き起こし、いたみを増加させます。
フローズン期…(筋拘縮期)
●肩を動かした時の痛みは、やわらぎます。
●しかし、肩関節が硬くこわばり、肩の動かせる範囲は制限されてしまいます。
ソーイング期…(回復期)
●肩関節のこわばりは、少しずつ改善します。
●そして、痛みや不快感も少なくなり回復に向かいます。
(さらに…)
関節のはなし
中高年に多い「変形性膝関節症」
年齢を重ねると、関節の痛みに悩まされることが多くなります。早い方では40歳くらいから違和感を覚え始め、60歳以上になると関節の不調を訴える方が急増します。
その悩みの中でもっとも多いのは、階段の上り下りや、立ち上がろうとするときに感じる痛み。これは「変形性膝関節症」と呼ばれ、ひざを長年使い続けることによって起こる老化現象のひとつです。
スムーズな動きに必要な成分
ひざ関節は大腿骨と脛骨、膝蓋骨の3つの骨から構成され、その表面は骨同士がぶつからないように軟骨で覆われています。
軟骨は非常に弾力性に富んでいて、クッションのようなはたらきで衝撃を吸収したり、関節をスムーズに動かしたりする大切な役割を担っています。このはたらきは、軟骨の構成成分であるコラーゲンやコンドロイチン、グルコサミンなどによって保たれています。
(さらに…)
発症
膝前十字靭帯損傷は、サッカーやラグビーなどのコンタクトスポーツにおいて相手チームの選手にタックルをされて膝をひねったり、バレーボールでの急な方向転換などで膝に過度の負担がかかった時に生じます。スキーなどでも多い膝の「けが」です。受傷後痛みが生じ、しだいに膝が腫れてきます。
病態
膝には4本の靭帯があり関節の動きをコントロールしています。それらが耐えられる以上の力が加わると靭帯が切れます。前十字靭帯は膝の関節の中にあるので、切れるとそこからの出血が関節にたまるのが特徴です。
診断には徒手的な診察が重要です。補助的診断法としてMRIが役に立つことが多いです。
(さらに…)
肉ばなれとは
☆自家筋力によるもの
こむら返り→筋肉がロックした状態
肉離れ→筋肉が引きはなされた時に起こる
筋・腱断裂
☆筋肉に外力が加わったもの
筋挫傷→強力な外力で叩かれて筋肉内に出血します
筋肉のケガにはいろいろな種類があります。
肉離れの起こり方
筋力はたがい違いに並んだ筋線維の束が収縮してかみ合うと発生します。ゴム紐と同じで、伸ばされながら収縮すると最大筋力が発生します。強く収縮した筋肉がそのまま固まってしまった状態がこむら返りです。その筋力に筋線維が負けたときに「肉離れ」は起こります。まれに、筋肉や腱が切れることがあります。
(さらに…)
症状、経過
腰椎分離症は、スポーツを活発に行っている10歳代前半の伸び盛りの青少年に、はじめは運動時の腰痛という形で出ます。運動の時には腰が痛いけれども、普段はなんともないといった程度で、運動を続けていくことも可能です。背中をそらす動作で腰痛が増すのが特徴で、しばしば前かがみも制限されます。
原因、病態
腰椎の後ろ半分は「椎弓」といってリング状の構造をしています。そのリングの斜め後方は細く弱い部分で、背中をそらす動作やジャンプからの着地のような動作で力が入ります。そういう動作が繰り返されると骨にひび(疲労骨折)が入ってきます。すべての人が分離症になるわけではなく、体質的な要因もあります。一番下の腰椎(第5腰椎)に好発します。
(さらに…)
捻挫のおこり方
バスケットボールやバレーボールで、ジャンプの着地で誤って人の足の上に乗ってしまったり、サッカーやラグビーで、グラウンドのくぼみや芝生に足をとられて、足首を捻ってしまうことがあります。足首の捻挫は、スポーツでおこる最も多い「けが」のひとつです。
捻挫の分類
捻挫とは、関節を支持している靭帯がいたむことです。靭帯のいたむ程度によって、捻挫の程度を三つに分けています。
1度の捻挫は靭帯が伸びる、2度の捻挫は靭帯の一部が切れる、3度の捻挫は靭帯が完全に切れると定義されています。
捻挫の症状
足首の捻挫は、多くは足首を内側に捻っておこります。そのため、足首の外側の靭帯がいたみます。外くるぶしの前や下に痛みがあり、腫れがみられます。また外くるぶしの前や下を押さえると、痛みがあります。
(さらに…)
スポーツ外傷とスポーツ障害
「スポーツ障害」とは、スポーツ活動中、身体に一回の大きな力が加わることによっておこる「ケガ」です。
一方、「スポーツ障害」とは、繰り返すスポーツ動作で身体の特定部位が酷使されることによっておこる「故障」です。「スポーツ障害」は別名、「使いすぎ症候群」と呼ばれます。
スポーツ外傷(ケガ);骨折、捻挫、脱臼、肉ばなれなど
スポーツ障害(別名、使いすぎ症候群)(故障);ジャンパー膝、オズグット病、野球肘、シンスプリントなど
(さらに…)